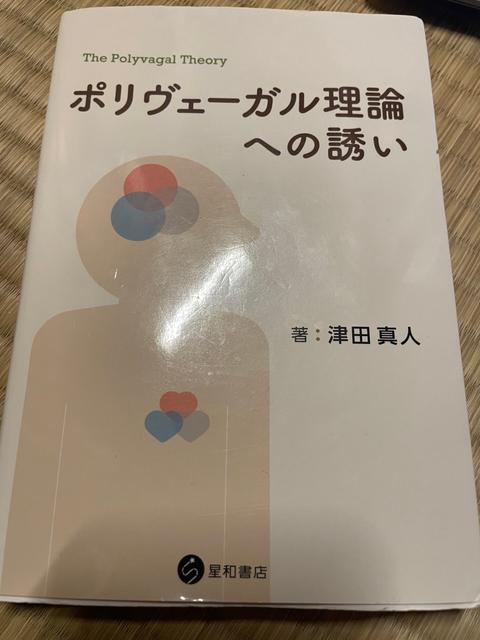聞きながら話しているという能力
今朝
車に乗っていたら
NHKのラジオで
【子ども科学相談】
がやっていた。
小学校生が
恐竜、昆虫、生物、天体、心など
科学に関する疑問を電話で質問して
それぞれの分野の専門家がそれに答えるというもの。
その中で
小学校1年生の男の子の質問に
「歌はなぜあるのですか?」
というのがあった。
その質問に対して
〝心〟
の専門家の女性の先生が
「人(類)が現れた時から歌はあるのでしょうね」
と言っていた。
この女性の先生の声はハスキーボイスで
ゆっくりで
なんだか声を聴くだけで
諭されているような気持になる。
いつも
どんな回答をするのか楽しみな人でもある。
私はそこまでの回答を聞いて車を降りたので
その後、女性がなんと回答したのかわからないのだけど。
今
明日のミーティングに向けて
この本を読みなおしている
以前もここで少し紹介したけど
この本の内容は
哺乳類には
2種類の迷走神経があるという理論、
その解説。
2つの内、新たに解明されたのが〝腹側迷走神経複合体〟
新たに解明されたけど
これは
古代の生物の鰓弓神経が由来。
5億年も前から存在し
魚類、爬虫類、両性類として変化していくときに
形を変えて生態と共に変化してきたもの。
特に
哺乳類となった時点でその働きは私たちの精神状態をも左右するものとなったという。
この新たな迷走神経の支配下にあるもの
それは
呼吸のリズム、頭部の傾き、回転(首の動き)、顔の表情、
発声、聴声、内分泌・免疫系、上咽頭
などの横隔膜より上の器官の機能。
これらは同じ腹側迷走神経複合体の支配下なので
互いに連動して機能する。
例えば
呼吸のリズムが穏やかなら心拍もしかり。
顔の表情も柔らかに。
首の緊張なく、頭を相手に傾け、
抑揚に富んだ声を出せる。
そんな自他の声を聴くことで
内分泌系、免疫系もおだやかに安定する。
あ
ちなみに
私たちは誰かに向けて発声する時に、同時に自分の声を聴いていて
絶えず自分の声を聴覚で確かめながら聞いているのです。
そうやって
無意識に声帯の筋肉や唇の形、息の速度や量を微調整してます。
また
他者の声を聴くときは、自分の中で密かに声を発していて
自分の内なる声でなぞりながら相手の声を聴いているんです
なので
発声とは聞くこと(聴声)
聴声とは発声なんですね。
これらはもちろん
心拍や表情にも関わります。
私が
ラジオの女性の先生の発声に魅力を感じるように。
発声する
声を聴く
これは
誰かがいて
成り立ちます
私たちは他人と関わる中で
無意識化でもこれら腹側迷走神経複合体働かせています。
これらは
社会を持つ哺乳類、
特に人において重要な
社会関与システムなんだと著者は言います。
(相手に影響するであろう)自分の声も見返したくなる、というものです。
で
今日の小学生の質問
「歌があるのはなぜか」
今の私が考えるその答えの一つは
「歌うことができるから」
そして
「聞くことができるから」
です!
声帯があり、気道がある
呼吸が出来て、表情筋を動かすことができる
さらに
歌を
リズムとして捉える耳がある
進化の過程でそれを獲得したから。
そして
それをすることで
自分や人の表情や心拍を変えることができるから
つまり
歌は
人だけがもつ
社会関与システムをフルに使うことができるもの
だから
歌をうたうんでしょう、
ということを
1年生にわかるように説明します
それが問題か(笑)